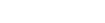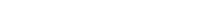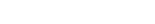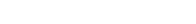高校野球7イニング制に関するアンケート
「子どもの権利とスポーツの原則」の視点から意見提出
日本ユニセフ協会は、日本高等学校野球連盟(以下、高野連)が、6月30日から7月11日にかけて実施した、「7イニング制に関するアンケート」に対し、ユニセフ「子どもの権利とスポーツの原則」の視点に基づいた意見を提出しました。
ユニセフ(国連児童基金)と日本ユニセフ協会は2018年11月に、国内外の専門家の協力と国内のスポーツ団体や企業の賛同を得て、スポーツと子どもの課題に特化した文書、ユニセフ「子どもの権利とスポーツの原則」(以下、原則)を発表しました。高野連も2019年8月に、子どもに関わる他のアマチュア野球13団体とともに、原則への賛同を表明されています。
高野連は、高校野球の部員数の減少や、夏季の熱中症リスク等、高校野球を取り巻く環境が変化する中、今年1月に「7イニング制等高校野球の諸課題検討会議」(以下、検討会議)を発足させ、高校野球における7イニング制の議論を始めています。本意見募集は、検討会議での議論の参考にするため、高野連がホームページ上で一般に広く意見を募集されたものです(以上、高野連ホームページの情報より)。
日本ユニセフ協会が提出した意見は、以下の通りです。
7イニング制に関するアンケート
近年、貴連盟が、年齢の枠を超え、けが防止や新たな指導者育成をはじめとする子どもの視点に立った環境づくりに取り組まれていることに敬意を表します。
全ての子どもの命と権利が守られるために活動するユニセフ(国連児童基金)を日本国内において民間として代表する立場にある日本ユニセフ協会として、貴連盟にも賛同いただいている「子どもの権利とスポーツの原則」(以下、「原則」)の視点から、現在貴連盟が実施されている「「7イニング制に関するアンケート」」(以下、「意見募集」)にあたり、下記の点を要望する次第です。
1.子どもたちの声を聴く機会を設けてください
「原則」は、賛同団体等に「年齢、及び成熟度に配慮の上、子どもが、試合や練習への要望や不快感を含め、自分に影響を与えるすべての事項に自由に意見を述べることを尊重する。トップアスリートを目指す子ども、レジャー、レクリエーションとしてスポーツを楽しみたい子どもを含め、スポーツとの関わり方、楽しみ方に関する子どもの意見を尊重する」ことを求めています【1. ii. 子どもの意見を尊重する】。また、同文が依拠する「子どもの権利条約」(以下、「条約」)第12条は、「自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する」としています。
今般の「意見募集」にあたっても、当事者である子ども、特に現役の高校生や、可能であれば将来高校で野球をしよう・続けようと考える子どもたちにも、安心して自身の考えを発信する機会を提供する※とともに、「条約」の主旨に基づき、貴連盟がどのように子どもたちの意見を受け止めたのかを子どもたちに説明・フィードバックする機会を設けていただくことを期待いたします。
※子どもの意見を募集する際には、匿名での意見の受付を可能にする等、成人とは異なる特段の配慮が必要と考えます。
2.子どものウェルビーイングの向上に資する改革の推進を期待します
高校野球は、国内では、他の子どもが参加するスポーツとは比較にならないほど「観る(魅せる)スポーツ=スポーツエンターテイメント」としての社会的地位を確立されています。長年にわたり多くの子どもたちの憧れの競技であり続けている高校野球ですが、参加する球児たちのほとんどは、アスリートである以前に、「条約」が定義する「子ども」です。まず問われるべきことは、「スポーツエンターテイメントとしてあるべき姿」ではなく、「高校野球に参加する子ども一人ひとり※の人権の尊重」、すなわち、「条約」が求める「子どもにとって最善の利益を第一に考慮すること」と考えます。
※「条約」の原題「The Convention on the Rights of the Child」のとおり、集団としての「子ども(Children)」ではなく「個々の子ども(the Child)」であることに留意が必要です。
上記の考え方は「意見募集」の(1)や(3)でも一部示されていらっしゃいますが、「原則」に賛同され、かつ社会的な発信・影響力をお持ちの貴連盟におかれましては、下に引用する「原則」2(スポーツを通じた子どものバランスのとれた成長に配慮する)も踏まえ、「7イニング制の是非の検討」に留まらない取り組み、すなわち、「条約」に順じ日本政府が「こども基本法」「こども大綱」で推進する、すべての子どものウェルビーイングの確保を目指す「こどもまんなか社会づくり」の一環として、改革を推進されることを期待いたします。
- 2 スポーツを通じた子どものバランスのとれた成長に配慮する子どもがスポーツ以外の安らぎ、家族とともに過ごす時間、レジャー、レクリエーションや学習とのバランスを通して、健全かつ包括的な個人としての成長を達成することを支援する。具体的には以下の視点に配慮し、団体、教育機関はその規模・性格・活動内容に応じた取り組みを検討する。
- i.子どものバランスのとれた成長を促進する
「子どもが家族と過ごす時間を尊重し、家族生活への権利を保障する。子どもが自分の性格、才能、精神的および身体的能力を最大限発揮できるよう、その年齢に適した学びや遊び、スポーツ、レジャー、レクリエーション活動に十分な機会を与え、文化芸術活動に自由に参加できる環境を確保し、バランスのとれた成長を促進する。スポーツにおける誠実性・健全性・高潔性、フェアプレーとチームワークを推進し、教育の重要性、健康でバランスのとれた食事とライフスタイルの重要性、いじめを含むあらゆる形態の子どもへの暴力からの保護など、日常生活の中でバランスのとれた成長を促進するために必要な様々な情報を子どもと共有する。また、トップアスリートとして活躍できる期間は限られていることや、事故や故障により「スポーツ活動の機会」が絶たれる可能性が常に存在するなど、スポーツ選手のキャリアに関わるリスクと危険性に関する情報についても子どもに提供する。 - ii.子どもの学習・教育の機会を確保する
トップアスリートを目指す子どもを含め、スポーツを行うすべての子どもに充分な学習の機会・時間を与える。子どもが、スポーツ以外の分野の学習や生活に関し、適切な資格を持った専門家に相談できる機会を提供し、子どもが将来スポーツ以外の進路を選ぶこともできるようサポートする。